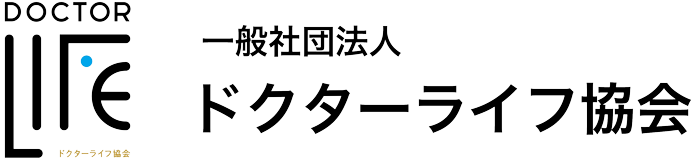昨今の、世界的かつ止まらない物価高に対する支援策として、2024年(令和6年)6月から「定額減税」が実施されることになりました。
納税者を対象に、所得税と個人住民税が1年間特別控除されます。
この記事では、定額減税の概要、減税される金額や方法、対象となる人物、メリット・デメリットなどについて解説していきます。
4万円の定額減税とは?いつから適用になる?
物価高の流れに対して、日本政府は給与所得の増加支援など、国民の所得を増やすための政策を打ち出しています。
定額減税もその政策の中のひとつですが、個人の可処分所得の増加につながる点から特に注目度が高くなっています。
定額減税とは、2024年4月1日に施行された「令和6年度税制改正法」に含まれる制度で、「納税者本人とその扶養家族1人につき、所得税3万円、住民税1万円の合計4万円が2024年の税金から控除される」というものです。
また、所得税や住民税の非課税世帯については、別途給付金支給制度が設けられており、低所得者の子育て世代も合わせて7万円~10万円が支給される予定です。
定額減税は、低所得世帯でも高所得世帯でもない中間層への恩恵が大きいことが特徴です。
物価高では多くの中間層が家計の圧迫を受けており、所得が低い人ほど収入に対する生活費の割合が大きくなるため、4万円の減税で得られる効果も大きくなります。
定額減税4万円の計算方法
定額減税は、以下のルールに則り実施されます。
いずれも自動的に適用となるため、基本的には手続きは必要ありません。
定額減税で減税される金額
●所得税・・・本人、扶養家族1人につき3万円の減税
●住民税・・・本人、扶養家族1人につき1万円の減税
給与所得者(会社員、扶養に入っていないパートアルバイト)の減税方法
●所得税・・・2024年6月徴収分より、合計3万円を徴収額から減税
(6月分で引ききれない場合は7月以降も継続)
●住民税・・・2024年6月分の徴収は無し
本来の年税額から1万円を引いた額を11分割し、2024年7月から2025年5月の11か月間で徴収する
給与所得者の所得税については、政府が、給与などを支払う企業に対し、減税額を給与明細に明記するよう義務づけることを発表しました。
実際にいくら減税されたかを示すことで、手取りの増加を実感してもらうという狙いがあります。
事業所得者(自営業、個人事業主)の減税方法
●所得税・・・予定納税がある場合は2024年7月の第一期から減税
(引ききれない場合は2024年11月の第二期も継続) 予定納税がない場合は確定申告時に減税
●住民税・・・2024年6月徴収分より、合計1万円を徴収額から減税
(6月分で引ききれない場合は8月分以降も継続)
年金所得者の減税方法
●所得税・・・2024年6月徴収分より、合計3万円を徴収額から減税
(年金の支給は2か月に一度のため、6月分で引ききれない場合は8月以降も継続)
●住民税・・・2024年10月徴収分より、合計1万円を徴収額から減税
(10月分で引ききれない場合は12月分以降も継続)
定額減税の対象となる人物
定額減税の対象となるのは、以下の点を満たす人物になります。
(1)2024年の所得税と住民税の納税者
(2)合計所得金額が1,805万以下の個人
※給与所得のみの場合は年収2,000万円以下の個人
※「子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除」を適用する場合は年収2,015万円以下の個人
(3)扶養親族として加算される条件として、「居住者」であること(海外にいる場合は定額減税の対象外)
注意が必要なのは、ざっくり言うと「年収2,000万円を超える高所得層は対象外となる」ということです。
また、今回の措置が「減税」であることから、そもそも非課税である世帯は対象外となります。
ただし、低所得層には給付金を支給する措置が取られることになっています。
1.住民税非課税世帯
2023年の時点で「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金」として3万円の給付がありました。
それに加えて7万円が追加され、合計10万円の支給となる予定です。
2.所得税非課税世帯で住民税の均等割りのみ支払う世帯
ここに該当する世帯は、これまで低所得世帯に当てはまらず、2023年の支援を受けられませんでした。
しかし、今回は新たに10万円が給付されることになりました。
2024年度に新たに住民税非課税世帯となった場合も、同様に対象となります。
また、上記1・2に当てはまる世帯のうち、18歳以下の子どもがいる子育て世帯には、子ども1人につき5万円が追加で給付されます。
定額減税の減税シュミレーション
定額減税では、世帯の扶養人数に応じて、減税額が増える仕組みとなっています。
例1)妻と子ども2人を扶養している場合、定額減税の合計額は16万円(所得税12万円、住民税4万円)
例2)共働きの世帯で扶養は子ども2人の場合、本人から見た定額減税の合計額は12万円(所得税9万円、住民税3万円)だが、配偶者も所得税3万円、住民税1万円が減税される
定額減税のメリットとデメリット
定額減税のメリットとデメリットをまとめると、以下のようになります。
●定額減税のメリット
・中間所得層を中心に、低所得層にも恩恵がある
・消費や購買意欲の増加が見込めるので、経済全体に活気が生まれることが期待できる
●定額減税のデメリット
・高所得層は対象外となり、恩恵を受けられない
・1年間限定の施策なので、持続的な効果が見込めない
定額減税のふるさと納税・住宅ローン控除への影響
定額減税は、住宅ローン控除やふるさと納税への影響はありません。
●ふるさと納税への影響
ふるさと納税の特例控除上限額(所得割額の2割)等については、定額減税前の所得割額とされています。
そのため、定額減税の影響はありません。
●住宅ローン控除への影響
定額減税の対象となる税額は、住宅ローン控除後の金額に適用されます。
よって、住宅ローン控除への影響はありません。
まとめ
2024年6月から定額減税が実施され、条件に当てはまる人は所得税3万円、住民税1万円の合計4万円が減税されます。
これらは自動的に適用となるため、手続きは基本的には必要ありません。
対象となる給与所得者の方は、給与明細に減税額が記されることになりますので、確認してみることをおすすめします。