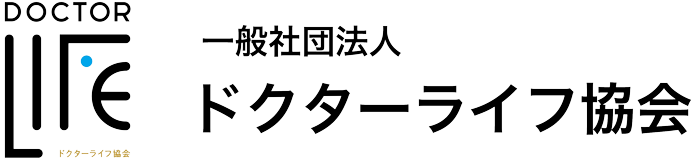年収が増えることは喜ばしいことですが、その裏でデメリットも発生します。
この記事では、年収が増えることで発生するデメリットについて解説していきます。
注意すべき「年収の壁」とは?
パートタイムで働く主に主婦の人に対して、よく「年収の壁」というものが挙がります。
これは、扶養の範囲内で働くことを目的とした際に、「税金・社会保険の扶養において決められた年収の上限基準を下回る必要がある」ということで、それらが年収の壁と呼ばれています。
ですが、実はパートタイム勤務ではない人にも気を配るべき「年収の壁」が存在します。
一定のラインを超えると税金が増えたり、控除や支援策の対象外となるため、それらは年収が増えることで発生する「デメリット」と言うこともできます。
年収が増えることで発生する6つの問題
年収が増えることで発生する6つの問題を紹介します。
【累進課税】所得税が増える
日本では、年収(所得)が増加するとともに、所得税も増えるようになっています。
これは「累進課税」と呼ばれる方式で、年間の所得に応じて税率が7段階で設定されています。
| 課税対象の所得額 | 税率 | 控除額 |
| ~195万円 | 5% | 0円 |
| 195~330万円 | 10% | 97,500円 |
| 330~695万円 | 20% | 427,500円 |
| 695~900万円 | 23% | 636,000円 |
| 900~1,800万円 | 33% | 1,536,000円 |
| 1,800~4,000万円 | 40% | 2,796,000円 |
| 4,000万円~ | 45% | 4,796,000円 |
年収が上がるにつれて税率も上がることが分かります。
特に、900万円のラインでは税率が23%から33%と大きく増加するので注意が必要です。
また、基本的には同時に住民税も増えるため、合わせて留意しておくことをおすすめします。
【850万円~】給与所得の控除割合が下がる
給与所得者には「給与所得控除」が設定されており、年間所得から一定金額を差し引いた部分が課税対象となります。
年収850万円までは段階に応じて控除額を算出する式が設定されていますが、年収850万円以上の控除額は195万円に固定となっています。
控除額が固定ということは、年収が上がるほど課税対象の金額が変わらないので、控除割合が下がっていくということになります。
【910万円~】高校授業料無償化の対象外となる
高校生の子どもを持つ家庭には「高等学校等就学支援金」が国から支給されることになっており、それにより公立高校の授業料は実質無償化されることとなっています。
2024年より、東京都は国公立私立関係なく、また所得制限なく全ての高校授業料を無償化するとしましたが、他県ではまだ所得による制限があります。
その所得制限は世帯年収が「910万円未満」となっているため、このラインを超える世帯は無償化の対象外となってしまいます。
県によっては補助支援策を設けていますが、それらの多くは910万円未満世帯に対する追加支援となっており、910万円を超える世帯への支援策は少なくなっています。
【960万円~】児童手当が受けられなくなる(~2024年10月まで※予定)
子どもがいる世帯に支給されている児童手当ですが、こちらにも所得制限が設定されています。
現状では、夫婦どちらかの年収が960万円を超えてしまうと、児童手当は支給されません。
2024年10月より、児童手当の所得制限を撤廃すると政府が発表していますので、こちらが実現すれば年収に関わらず全ての子どもがいる世帯が児童手当を受給できるようになります。
【2400万円~】基礎控除が減額されていく
所得控除のうち、基礎控除は原則としてすべての人に該当する控除です。
控除額は原則として48万円ですが、適用には所得制限があります。
年間の所得が2,400万円以下であれば、基礎控除は48万円満額が適用されますが、2,400万円を超えると徐々に基礎控除は減額されていき、年収2,500万円以上になると基礎控除の対象外となってしまいます。
【3000万円~】住宅ローン控除が使えなくなる
住宅の購入や、増改築を行う場合には住宅ローン控除を受けることができます。
一般住宅であれば年間最大40万円の控除となり、最長で10年の間、ローン残高の1%が住民税及び所得税から控除されます。
この制度にも所得制限があり、年収3,000万円以上になると住宅ローン控除の対象外となってしまいます。
まとめ
紹介した6つは「デメリット」ではありますが、これらのラインを気にして収入を抑えることは、基本的には得策ではありません。
年俸制や月俸制の場合は特に、今後の自身の評価に関わってくるからです。
各項目のライン付近の収入の方は、各事項に自分が当てはまるということを理解して心づもりをしておくことをおすすめします。
その上で、配偶者の収入等で調整がきく場合は、内容と合わせて調整の検討するのもよいでしょう。